9月は日本を含む世界の株式市場が軒並み不調で、苦しい月となりました。
ロシアによるウクライナ侵攻や物価高に加えて、経済協力開発機構(OECD)による景気の下方修正や、FOMCによる利上げの継続が大きな要因となっています。
また、今後も株式市場や景気の停滞が懸念されており、どのような投資ポジションに立つべきか判断するのは難しいです。

今回は、9月の経済トピックスについてお伝えしていきますので、今後の投資方針を決定する際の参考にしてください。
文字多めですがぜひ最後までご覧ください。
日本の9月の経済動向・トピックス
まずは、日本の9月の経済動向やトピックスについて見ていきましょう。
中見出し 日経平均・TOPIXの推移
9月末の日経平均株価の終値は25,937.21円で前月末から1.724.26円(-6.23%)ダウンしました。


また、9月末のTOPIXは1,835.94ポイントで前月末から99.55ポイント(-5.14%)ダウンしました。


いずれも8月末から下落しており、9月の株式市場はかなり不調だったことが分かります。
9月末の段階で税引き前の配当利回りが4%を超えている企業数は
・東証プライムが356社
・東証スタンダードが215社
・東証グロースが3社
という結果に終わりました。
株価の下落に伴って配当利回りが高まり、前月よりも配当利回りが4%を超えている企業数が増えました。
様々な経済レポートでも世界経済の停滞や失速の可能性が示唆されていますが、日本の株式市場の雰囲気もかなり悪いと言えるでしょう。
しかし、4~6月期の全産業の経常利益は28.3兆円で過去最高を記録するなど、明るい話題もあります。
そのため、個別株を物色する際には、「安定して利益を上げられているか」「今後も安定して事業を継続できるか」という点にフォーカスすると良いでしょう。
とはいえ、原材料価格の高騰や欧米の利上げに伴う経済活動の停滞などの悪い要素の方が強く、相場を悲観する人が多いという状況です。
景気動向指数について
内閣府が発表した7月の景気動向指数は、前月比1.4ポイント低い98.9でした。
景気動向指数とは、経済に重要かつ景気に敏感な30項目の景気指標を基に算出する指数で、景気全体の現状を知ったり将来の動向を予測する際に役立つものです。
なお、内閣府は景気の基調判断を「改善を示している」のまま据え置いていますが、今年に入ってからの景気動向指数について見てみると、
・1月:101.3(前月比−1.6ポイント)
・2月:100.2(前月比−1.1ポイント)
・3月:100.7(前月比+0.5ポイント)
・4月:102.3(前月比+1.6ポイント)
・5月:100.7(前月比−1.6ポイント)
・6月:100.3(前月比−0.4ポイント)
・7月:98.9(前月比−1.4ポイント)
上記のように推移しています。



下落が続いている上に、7月は下落の幅が広がっていることから、今後の経済の見通しはかなり暗いと言えるでしょう。
景気ウォッチャー調査
景気ウォッチャー調査とは、「街角調査」とも呼ばれており、地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々の回答を基に作成するものです。
内閣府が9月8日に発表した8月の景気ウオッチャー調査は49.4となり、前月から6.6ポイント上昇しました。(上昇は3カ月ぶり)
街角にいる人たちは、「新型コロナウイルスで低迷した経済社会活動が正常化する」ことを期待していますが、まだ好不況の分かれ目である「50」を下回っています。
つまり、前月から改善傾向にあるとはいえ、まだまだ回復を実感できるレベルには無い、と言えるでしょう。
なお、今回の調査結果を受けて、内閣府は「景気は、持ち直しに足踏みがみられる。先行きについては、価格上昇の影響等を懸念しつつも、持ち直しへの期待がみられる。」とまとめています。
街角の心理的には景気の好転を感じているようですが、今後の物価高や株式市場の停滞などを受けて、どのように変化するのか、引き続き注意が必要です。
貿易統計について
財務省が9月15日に発表した8月の貿易統計速報によると、8月の貿易収支は2兆8173億円の赤字でした。
ウクライナ侵攻の影響でエネルギー価格が高騰し、またアメリカの利上げに伴う円安の影響から、輸入額が前年同月比49.9%増となっています。
なお、貿易赤字は13カ月連続となっており、貿易赤字が続くと日本経済にジワジワとダメージを与え続けることになります。
また、貿易赤字は円安を進める要因にもなることから、今後の為替市場にも小さくない影響を与えるでしょう。
日本は円安に苦しんでいますが、今後も貿易収支の赤字が続くと、円安状態は長引く可能性が高いです。
政府の月例報告
政府の9月の月例経済報において、国内景気の総括判断を「緩やかに持ち直している」と据え置きました。
「緩やかに持ち直している」という判断は3カ月連続で、今後の先行きに関しては「金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある」としています。
日本は相変わらず利上げすることなく金融緩和を続けていますが、米欧各国では積極的に利上げを行っています。
現在、円安となっている大きな要因は「金利差」ですが、金利差が広がっていくと円の魅力が無くなり、円安がさらに進むことになります。
円安状態が継続すると、輸出企業の利益が圧迫されたり、インフレが進み消費者心理が冷え込んでしまいます。
その結果、日本経済は停滞してしまう可能性が高いため、政府としても月例報告の中で為替や世界各国の金融政策に留意していると言えるでしょう。
なお、世界景気に関しては前月の「持ち直しのテンポが鈍化している」から「緩やかな持ち直しが続いている」としています。
日銀の為替介入
1ドル140円台の円安状態を受けて、日銀は9月22に24年ぶりの為替介入(円を買ってドルを売る)が行われました。
為替介入とは、政府が外国為替市場で通貨間の売買を行い、為替相場に影響を与えることです。
為替相場の急激な変動を抑え、安定化を図ることを目的として行われますが、滅多に行われるものではありません。
今回の日銀による為替介入は3兆円規模と言われており、市場に流通している円を買うことで円高へシフトしようとしたわけです。
実際に、為替介入が行われる直前は1ドル146円台でしたが、為替介入直後は一時的に1ドル140円台までと円高に触れました。
しかし、その後は1ドル144円台に円安に振れるなど、為替介入の効果は限定的です。
つまり、為替介入という政府の大きなアクションが行われても、「円安のトレンドが大きく変わることはなさそう」という状況です。
とはいえ、財務省は追加の為替介入も示唆しているため、今後も為替相場が激しく動くことが予想されます。
日本の9月の経済景況まとめ
日経平均とTOPIXが前月から下落するなど、日本株に失速の気配が見られます。
しかし、株価とは逆に業績が安定している企業も多いことから、配当利回りが高まる「うまみ」を感じることもできます。



円安で良い影響を受けている企業や、安定的に利益を出している企業の株があれば、「様子を見て買う」というスタンスが無難と言えるでしょう。
もちろん、リスク要因も多くあるため、ストレスを感じない範囲で投資することが大切です。
海外の経済動向・トピックス
続いて、海外の経済動向やトピックスについて見ていきましょう。
アメリカの経済指標の推移
9月末のS&P500指数は3,585.62ポイントで、前月比-381.23(-9.61%)という結果でした。


また、NYダウの9月末の終値は28,725.51ドルで、前月比-2,930.91ドル(-9.26%)という結果に終わり、9月も株式相場はかなり不調でした。


なお、S&P500の9月の下げ幅は、20年ぶりの大きさで、S&P500、NYダウ、ナスダック総合指数の全てが年初来安値です。
詳しくは後述しますが、FOMCによる利上げ継続の表明を受けて、今後もますます株安が進行することが懸念されています。
FOMCでの利上げ
9月21日に行われたFOMC(米連邦公開市場委員会)において、3回連続で通常の3倍にあたる0.75%の利上げを決定しました。
なお、会見でパウエル議長は「利上げは2023年も続ける」「インフレを抑制することが最優先」という姿勢を示しています。
一般的に、金利の上昇は株価にとってマイナス要因となるため、早いペースで利上げが行われていることで、アメリカ経済は減速しているというわけです。
アメリカは世界の金融の中心なので、アメリカ経済が停滞すれば、日本を含めた世界経済が減速します。



そのため、次回11月に行われるFOMCや、アメリカ政府が公表する経済指標は要注目と言えるでしょう。
経済協力開発機構(OECD)の発表
経済協力開発機構(OECD)が公表した経済見通しにおいて、「下方リスクが大きい」と明記されています。
また、2023年は多くの国が景気後退に陥る恐れがあり、実際に2023年の世界の実質成長率を2.2%に落ち込むという認識を示しました。
一般的な実質成長率は3.0%なので、世界経済の停滞は明らかです。
実際に、新型コロナウイルスが蔓延する前の2019年まで10年間の平均実質成長率は3%を超えていたため、景気の見通しはかなり暗いと言わざるを得ません。
ロシアのウクライナ侵攻による物価高やインフレ対応に伴う利上げが経済の重荷となっており、世界景気の回復は鈍化すると考えられています。
世界9月の経済景況まとめ
アメリカをはじめとした世界経済は停滞しており、FOMCの影響を受けて停滞が長引く可能性があります。
パウエル議長も「景気の回復よりもインフレの抑制の方が大切」という立場を取っているため、今後も経済が急回復するビジョンは見えづらいです。
しかし、株式市場が停滞する期間が長引くと、財務が優良で安定している企業の株を割安で仕込めるチャンスでもあります。
そのため、米国株や米国ETFは、「様子を見ながら、欲しい株に割安感が出てきたら購入」というポジションが無難です。
9月の経済トピックスまとめ
9月の日本経済と世界経済のトピックスについてお伝えしてきました。
日本株をはじめ、アメリカの株は軒並みマイナスとなっているため、保有資産が目減りしている人も多いでしょう。
日本株式に関しては、企業業績は悪くないものの、景気後退の兆候やリスク要因は数多くあります。
円安が止まらない状況を受けて、政府が為替介入するという事態に発展しましたが、効果は一時的に留まっています。
経済協力開発機構(OECD)も景気の見通しを下方修正している通り、今後の世界経済に関する明るい話題が少ないのが現実です。
ウクライナ情勢は相変わらず不安定で、世界各国のインフレが収まる気配も無いことから、しばらくは株式市場の停滞や原則に備える必要があるでしょう。



逆に言えば、優良企業の株を割安で仕込めるチャンスでもあるため、早い段階で目星を付けておき、しかるべきタイミングで購入できるように準備するのがおすすめです。
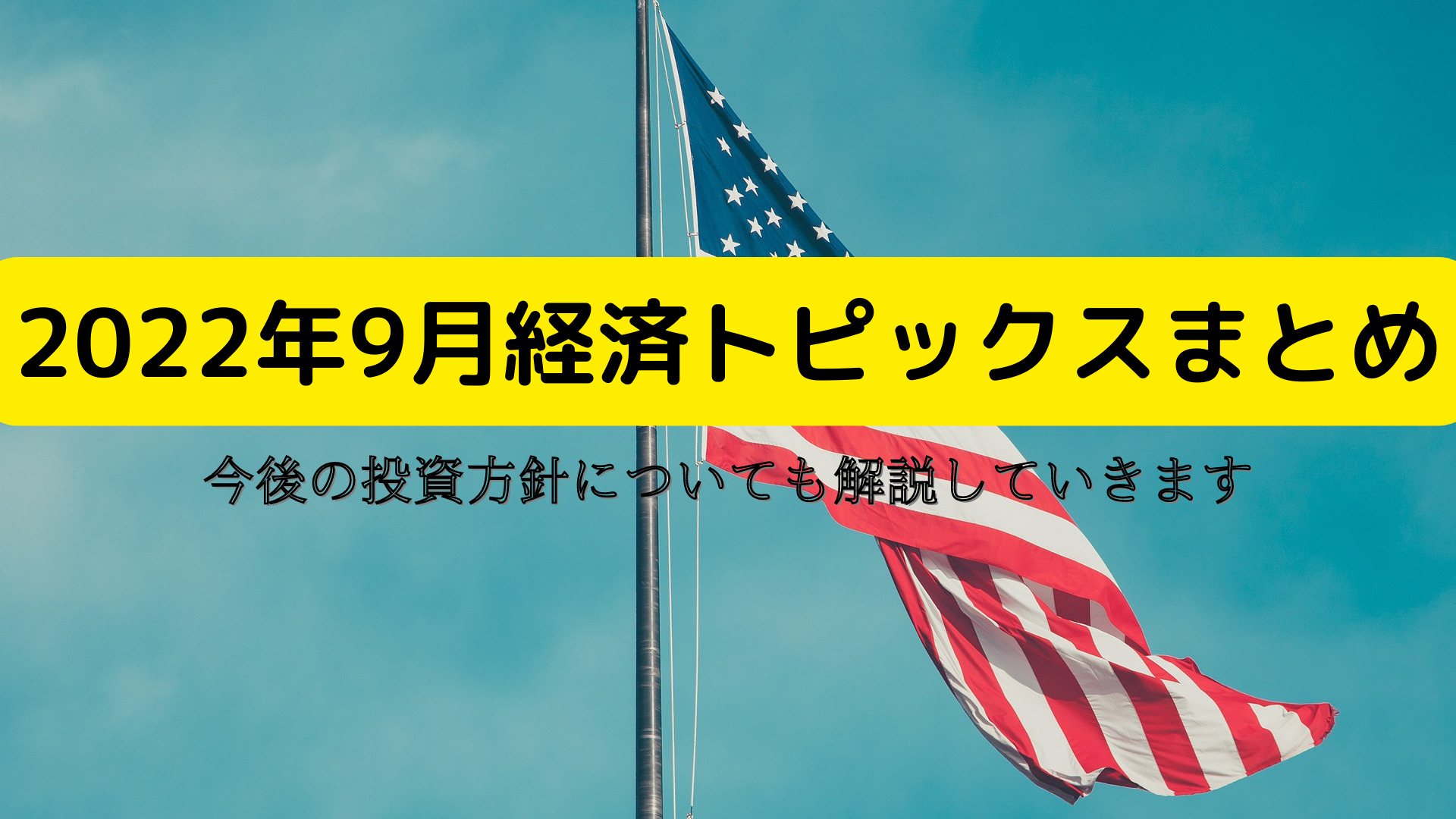
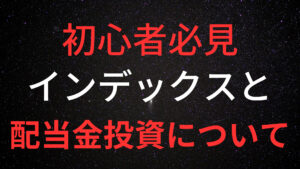
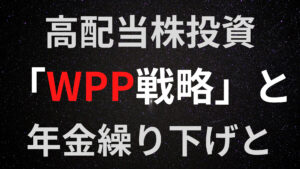
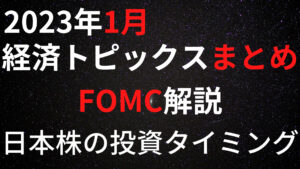
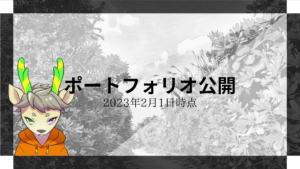

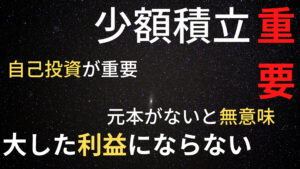
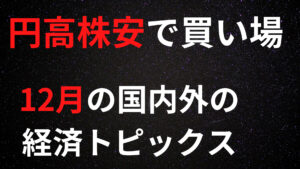

コメント