12月13~14日にアメリカでFOMCが開かれ、利上げ幅が0.75%から0.5%に縮小されることが決定しました。
依然としてインフレ率は高い水準ですが、国際的な原油相場の下落などの影響もあり、5ヶ月連続で伸びは鈍化していることから、「インフレのピークは超えた」という見方が広がっています。
しかし、パウエル議長は、「物価上昇率を目標の2%に抑えるためには今後も利上げを続けることが適切」と述べており、今後もインフレ退治を優先する意向を示しています。
また、金融引き締めの長期化に伴う景気の悪化が懸念されており、記者会見では今後の投資判断をする上で重要な質疑応答もされました。
今回は、12月13~14日に開かれたFOMCについて、パウエル議長の発言の要旨や今後の展望を含めて解説していきます。
利上げ幅は0.5%に縮小

12月13~14日にFOMCが開かれ、FRBのパウエル議長は「利上げ幅を0.75%から0.5%に縮小する意向」を示しました。
FRBは、利上げペースを減速しつつも、2023年末の政策金利見通しについては中央値4.6%から5.1%に引き上げて金融引き締めを継続する考えです。
また、記者会意において「物価上昇率を目標の2%に抑えるためには今後も利上げを続けることが適切」と述べ、利上げ継続の方針を示しています。
パウエル議長は、先日発表されたアメリカの消費者物価上昇率が鈍化したことをポジティブに捉えつつも、「インフレが持続的に低下していることを確信するには、さらに多くの証拠が必要」と述べています。

これは、「まだまだインフレが続く可能性があるから、金融引き締めは続けますよ」という意思表示です。
政策金利の到達点の予想に関して、「再び引き上げることがないとは自信を持って言えない」と述べていることから、今後のインフレ率によっては政策金利のさらなる引き上げが行われる可能性があります。
今回示された見通しによると、次回の会合から利上げ幅を通常の0.25%に戻した場合、2023年に入ってから3回目の会合にあたる5月のFOMCを最後に利上げを停止するシナリオが有力です。
なお、積極的な利上げ姿勢が示されたことでリスク回避・景気悪化を懸念した売りが広がり、14日のNYダウは前日比142ドル安の3万3966ドルとなりました。
アメリカ経済の減速は続くか?
アメリカ経済の減速懸念が続いています。
コロナ禍からの経済回復局面で、米経済は企業の求人が急増した一方、急激なインフレと金利の上昇を受けて実質可処分所得の低下や個人消費の鈍化が顕在化しているためです。
11月の米消費者物価指数(CPI)は前年同月比7・1%の上昇となり、5カ月連続で伸びが鈍ったものの、人手不足による賃金上昇などの影響もあって、依然として記録的な高水準が続いています。
FRBは、以前から「経済を悪化させてでもインフレ退治を優先する」姿勢を明らかにしていましたが、今後も金融引き締めが継続される可能性が高いです。
パウエル議長は、会見の中で「景気後退になるかどうか、そうなった場合、それが深刻なものになるかどうかも分からない」と述べており、今後も不確定要素が多くある懸念を示しました。
アメリカ国内での人手不足による労働供給の枯渇が発生、中国のゼロコロナ政策による供給網の混乱など、景気悪化を増幅させるリスクを多く孕んでいます。
今回のFOMCで金融引き締めが長期化する懸念が強まり、アメリカをはじめとした世界経済の失速が起こる可能性は高いと言えるでしょう。
FRBも経済失速と失業率悪化を想定
FRBは、今後アメリカ国内の失業率が悪化し、経済成長が失速する見通しも示しています。
発表の中で、来年のGDP成長率は2022年と同じ0.5%として、来年の予測は「緩やかな経済成長」「リセッションに該当するとは思わない」と述べてはいるものの、実際には停滞に近い状態になると予想しています。
9月公表の見通しでは、来年のGDP成長率は1.2%となっていたことから、見通しを大幅に引き下げたことになります。
また、失業率は現在の3.7%から2023年末には4.6%に悪化すると見込んでおり、雇用情勢の悪化予想もしています。
アメリカ経済の減速が懸念されている中で、今後のインフレ率によっては金融引き締めが継続される公算が高いです。
FRBは、今後もインフレ退治を優先して物価の安定を最優先で考えていることから、株式市場にとってはネガティブな状況が続くと考えられます。
円安トレンドは続く
利上げ幅は縮小したとは言え、アメリカでは引き続き利上げを行う方針です。
しかし、日本では相変わらず利上げを行わない方針を続けています。
12月19日~20日に日銀の金融政策決定会合が行われますが、「金利は上げない(上げられない)」と予測する人が多いです。
つまり、今後も日米の金利差は広がっていく公算が高く、引き続き過去の水準から見て円安トレンドが続くと考えます。
1ドル150円台の円安にはならなくとも、130~140円台で推移する可能性が高いと言えるでしょう。
日本企業に関して言うと、円安による恩恵を受けている企業にとっては追い風で、円安によって打撃を受けている企業にとっては向かい風となる状況が続くと考えられます。
記者会見の質疑応答


続いて、パウエル議長の記者会見の要旨を一部抜粋して紹介していきます。
インフレ圧力が明確に弱まる前に「スタグフレーション」が発生した場合、金融政策にどう影響するか
現在の労働市場はとても逼迫している。我々は物価安定と雇用の最大化を目標としているが、物価安定が当面の優先事項となる。
物価上昇率を2%に抑える目標を見直す可能性はあるか
考えていない。この先も考えることはない。
失業率が来年にはほぼ1%上昇を予想しているが、これはリセッション(景気後退)の予測ではないのか。
経済成長を続けるとの見込みがある限り、リセッションとはいえない。ただ、4.7%の失業率というのは依然として強い雇用情勢を示している。ハイテク業界を除けば、企業は人員削減を控える傾向になっている。
直近のインフレ圧力の緩和は一時的なものなのか。経済のソフトランディング(軟着陸)の可能性についてどう考えているか。
ここ2カ月でインフレ上昇率が鈍化したことは歓迎すべきことだ。しかし消費者物価指数(CPI)のコアインフレ率は6%で、これは我々の目標(2%)の3倍にあたる。つまり、物価が安定するには長い道になることを理解する必要がある。
ソフトランディングはもはや不可能ということか。
不可能といっているわけではない。インフレ退治が長期戦になり、高金利を維持しなければいけない場合にはソフトランディングの可能性は狭まるかもしれない。しかし、インフレ率が継続して低下すればソフトランディングも可能だろう。景気後退が起こるのか、またどれくらい深刻になるかは誰にもわからない。
2023年に利下げに転じる可能性はあるのか。
現在は長期的なインフレ率を2%に抑えるために金融引き締めを維持することに注力している。過去の経験から、早急な緩和には十分注意しなければならない。利下げについては検討していない。
11月の会合以降、債券や株式相場が回復したが金融政策への影響はあるのか。
我々のスタンスはまだ十分に引き締め気味になったとはいえないので、今後も利上げを続けていくことが適切だと考える。現時点で、ピークの金利を引き上げないと自信をもって言うことはできない。
来年の利上げのペースは。
政策スタンスが引き締め気味になった現在、利上げのペースはそれほど重要でなく、「最終的な金利の上限」の方がより重要だ。インフレと景気の状況次第で利上げの幅を決める。金利のピークをどれだけ維持するかは、我々がインフレが低下しそれが持続できると自信を持てるようになるかどうか次第。
来年は2月の会合以降0.25%ずつの利上げをする方向か。
まだ方針は決めていないが、おそらくそうなると思う。これまで急速に大きな利上げを実施してきただけに利上げのペースを緩めるのは適当だと思う。
11月のFOMCまとめ
今回のFOMCで、パウエル議長は物価上昇率を2%に抑える目標を見直す可能性を完全に否定しました。
なお、消費者物価指数(CPI)のコアインフレ率は6%で、FRBが目標としている2%の3倍にあたることから、引き続き金融引き締めを継続する意向です。
ソフトランディングに関して「不可能といっているわけではない」としつつも、金融引き締めの長期化に伴う景気の悪化が起こるリスクは高いと言えるでしょう。
なお、アメリカの指揮者では2023年中に利上げを打ち止めし、5%程度の政策金利をしばらく維持して「インフレが収束する見通しが立った」タイミングで、徐々に利下げを始めるシナリオが有力視されています。
今後のアメリカ経済・世界経済が悪化すれば、当然日本経済にも悪影響が及ぶため、投資家としては「景気悪化に備えてキャッシュを用意しておく」重要性が高まっています。
今後、日本で行われる日銀の政策決定会合にも注目しつつ、どのような投資ポジションを取るべきか判断していきましょう。

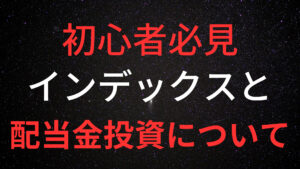
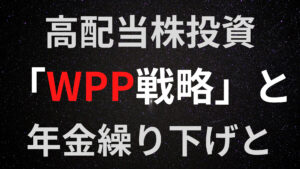
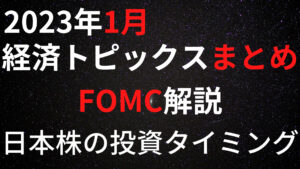
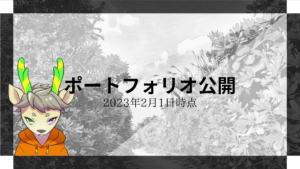

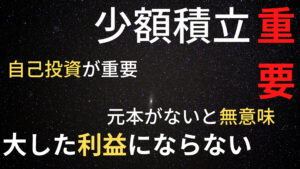
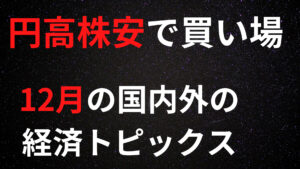

コメント