近年は投資を行う人が増えていますが、投資初心者の人から人気があるのが、AIを用いて自動で投資判断をしてくれる「ロボアド」です。
自分にとって最適なポートフォリオを組み、自動で買い付けをしてくれる機能が搭載されているので、心理的にも取っつきやすい魅力があります。
しかし、結論からお伝えするとロボアドの利用はおすすめしません。
今回は、近年注目と人気を集めているロボアドの特徴や、おすすめできない理由などを解説していきます。
証券会社が提供しているロボアドとは
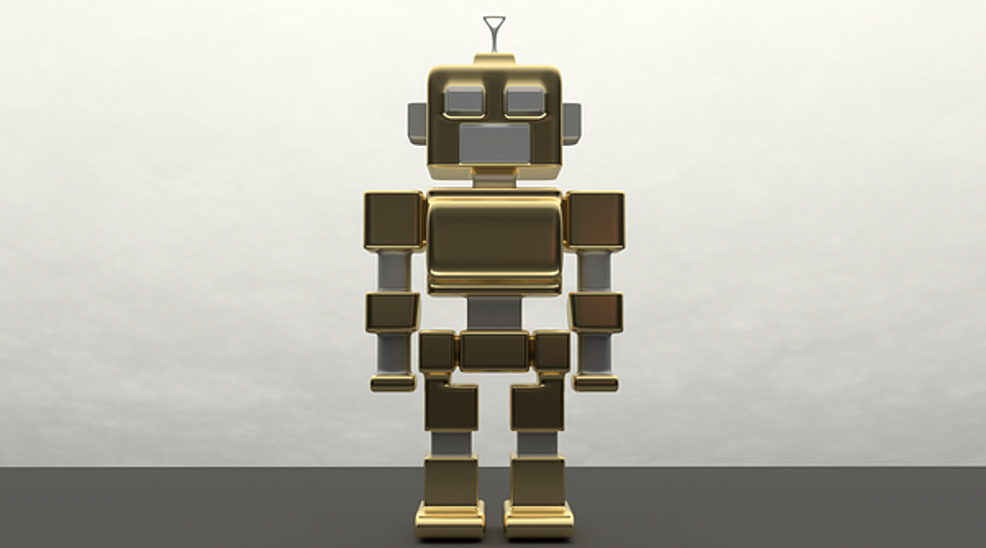
ロボアドとは、「ロボアドバイザー」の略で、投資家個人に代わって資産運用のアドバイスや運用のサポートしてくれるサービスです。
いくつかの質問やアンケートに答えることで、AIが利用者のリスク許容度を測定して最適な資産の組合せ(ポートフォリオ)を提案する便利な機能が搭載されています。
最近は、投資家が資金を口座に入金しておくだけで、ポートフォリオに応じて自動で買い付けをしてくれる機能も付いています。
「どれを買えばいいのか分からない…」という人でも投資しやすいため、投資初心者を中心に高い人気を得ています。
金融機関にいる人間が行うラップ運用のコンピューター版といった形で、購入後の資産のリバランスなども行ってくれるロボアドが多いことから、投資に時間を割けない人にとってはありがたいサービスでしょう。
なお、ロボアドは長期的な運用を想定しているので、投資信託やETFが主な投資対象となっています。
「提案型」と「投資一任型」の2タイプがある
ロボアドには、投資に関するアドバイスだけを受けることができる「提案型」と、実際の運用まで任せられる「投資一任型」の2種類があります。
「提案型」は、アンケートなどに答えるだけでその人にとって最適なポートフォリオを「提案するだけ」であり、無料で利用できます。
実際に運用する際には、ロボアドの提案を参考にしながら自分自身で投資信託などを購入することになります。(もちろん、ロボアドの提案を無視しても構いません)
「投資一任型」の場合、投資家個人に合わせた金融商品の買い付けだけでなく、リバランスなども行ってくれます。
この場合、投資をロボアドに一任することになるため、利用にあたって手数料を負担しなければなりません。
ロボアドのメリット
ロボアドには様々なメリットがあります。
投資家に代わって投資判断を下してくれることから、「人間の負担」を大きく軽減してくれる点が大きなメリットです。
専門的な投資の知識が不要
「投資や経済の勉強をするのは面倒くさい!」という人にとっては、ロボアドは魅力的なツールと言えます。
ロボアドはAIが投資家にとって最適なポートフォリオを組み、自動で買い付けを行ってくれるので、投資家のやるべきことは「入金する」だけです。

日経新聞を読んだり、株価のチャート分析などをする必要が無いことから、全くの初心者でも気軽に投資ができることが分かるでしょう。
そのため、投資を始める心理的ハードルは低く、勉強したり新聞を読むのが苦痛という人に向いています。
感情に左右されることなく資産運用が可能
投資を行う際には、上昇局面だろうが下落局面だろうが「市場に居続けること」がリターンを得る上では重要となります。
しかし、人間には感情がある以上、保有株式が暴騰したり急落したら感情に「ブレ」が出てしまい、結局損をしてしまうことが少なくありません。
一方で、ロボアドは仕組まれているアルゴリズムに則って運用されているので、感情に関係なく機械的にデータやルールに基づいた資産運用をすることが可能です。
「ついつい相場が気になってしまう」「急落すると慌てて投げ売りしてしまうかも…」という人にとっては、ロボアドが向いていると言えるでしょう。
ロボアドがおすすめできない理由


投資初心者や投資に割ける時間が無い人にとって、ロボアドは非常に魅力的なサービスです。
しかし、冒頭でお伝えした通り、投資をする上ではロボアドの利用はおすすめしません。
以下で、ロボアドがおすすめできない理由を解説します。
多くの金融機関がロボアドのサービスを提供していますが、ロボアドでの運用に関する手数料は運用資産残高に対して「年率1%前後」のものが多いです。
手数料が高い
「手数料1%」を高いと判断するか安いと判断するかは、個々人の価値観によって分かれるでしょう。
しかし、近年は手数料(信託報酬)が0.2%以下で保有できる優良なインデックスファンドが多く出ていることから、ロボアドの手数料は「やや高い」と言わざるを得ません。
もちろん、買い付けや資産配分のリバランスを自動で行ってくれるので、投資家個人の手間を大きく省いてくれる魅力はありますが、手数料は「投資家にとって確実なマイナスリターン」です。
実際、ロボアド経由では無くネット証券から自分で商品を選択して購入した方が、手数料が安くなるケースがほとんどです。
つまり、投資経験が無い人や何らかのサポートを受けたいと考えている場合は、無料で利用できる「提案型」で提案だけ受け、ニーズに近い投資信託を買う方が合理的です。



運用期間が長期になればなるほどロボアドの手数料負担は大きくなるので、手数料を軽視するべきではありません。
そもそも投資の本質から離れている
そもそも、投資とは「自分の頭で考え、自分の身銭を切って行うもの」です。
自分で考えて結論を出して購入した商品であれば、もし下落に巻き込まれてマイナス評価となっても一定の納得感がありますが、ロボアドに一任してマイナス評価が出ても怒りのやり場がありません。
投資は「自己責任」が原則で、自分でリスクの許容度を把握して、自分で責任を取ることが投資の本質なのです。
ロボアドを活用して投資を行って損失が出て、金融機関に対して怒りを表したところで相手にしてくれるわけがありません。
業者やAIに任せて運用が失敗して納得できなかったとしても、それは「自分の頭でしっかりと考えずに任せた結果」に他ならないので、しっかりと自分の頭で考えることが重要です。
なお、運用方針の決め方に関しては、投資に関する本を2~3冊読めば人でも十分に判断できるようになるので、そこまで難しいものではありません。
また、投資に限った話ではありませんが、失敗をすることで得られる知識は非常に貴重なものです。
自分の頭で考えて実体験として学び、「自分で判断できようになる」メリットも享受できるでしょう。
AIでも元本保証はできない
リーマンショックやコロナショックなどの暴落や、市場の下落が続くような時期は起こりえます。
実際、これまでも10年に一度くらいのペースで株式市場の暴落は起こっているので、投資をする際には「暴落はいつか必ず起こりうる」という心構えでいる必要があります。
投資初心者は「AIであれば上手に切り抜けてくれるだろう」と思いがちですが、このような市場が苦しい時期でも、残念ながらAIやロボットだからといって上手に運用してくれるわけではありません。
市場全体が下がるような状況であれば、いくら優秀なアルゴリズムが仕込まれたAIが運用していても、残念ながら資産残高は減ります。
つまり、いくら優秀なロボアドであっても、投資をする以上は「元本保証はあり得ない」点は知っておきましょう。
株式市場は自分とは全く関係や責任の無いところで暴落するなど、理不尽なことが起こりえます。
そのような理不尽なリスクを受け入れつつ、自分なりにトライアンドエラーをすることが重要と言えるでしょう。
個人の資産全体を把握できない
資産運用をする際には、「自分が持っている全資産」を把握した上で取るべきリスクを決定するのが基本です。
ロボアドには個人の資産全体を完全に把握できないデメリットもあるため、これもロボアドがおすすめできない大きな理由となっています。
実際にロボアドを活用している人であっても、ロボアドに全財産の資産運用を任せるのではなく、資産の一部を任せる人がほとんどでしょう。
投資家にとっては、ロボアドに任せる部分の運用資産ももちろん重要ではありますが、ロボアドに任せる部分以外の資産全体の運用状態の方がはるかに重要です。
ロボアドを利用するにあたっては、現在の資産状況やリスクに対する考え方などを回答して、ロボアドに最適なポートフォリオを提案してもらうことになりますが、ロボアドの情報収集能力は完全ではありません。
つまり、ロボアドに一部の資産の運用を任せてしまうと、「ロボアドで運用している資産」と「ロボアド以外で運用している資産」を分けて考えなければならない手間が発生してしまうのです。
結果的に、「自分で手間暇をかけて資産を管理している」という状況になるのであれば、そもそもロボアドを使う必要は無かった、ということにもなりかねません。
まとめ
ロボアドは、投資初心者にとって便利なツールであることは確かです。
しかし、投資とは基本的に「自分で考えるもの」であり、自分が許容できるリスクの大きさを判断できるのは自分だけである以上、投資判断をロボアドに頼るのはおすすめしません。
資産運用をする際には「自分で考えて、自分が納得できる形で行う」ことを肝に銘じておくことが重要です。
無駄な手数料を支払うこと無く、自分の頭で考えて最適な投資を着実に実行していきましょう。
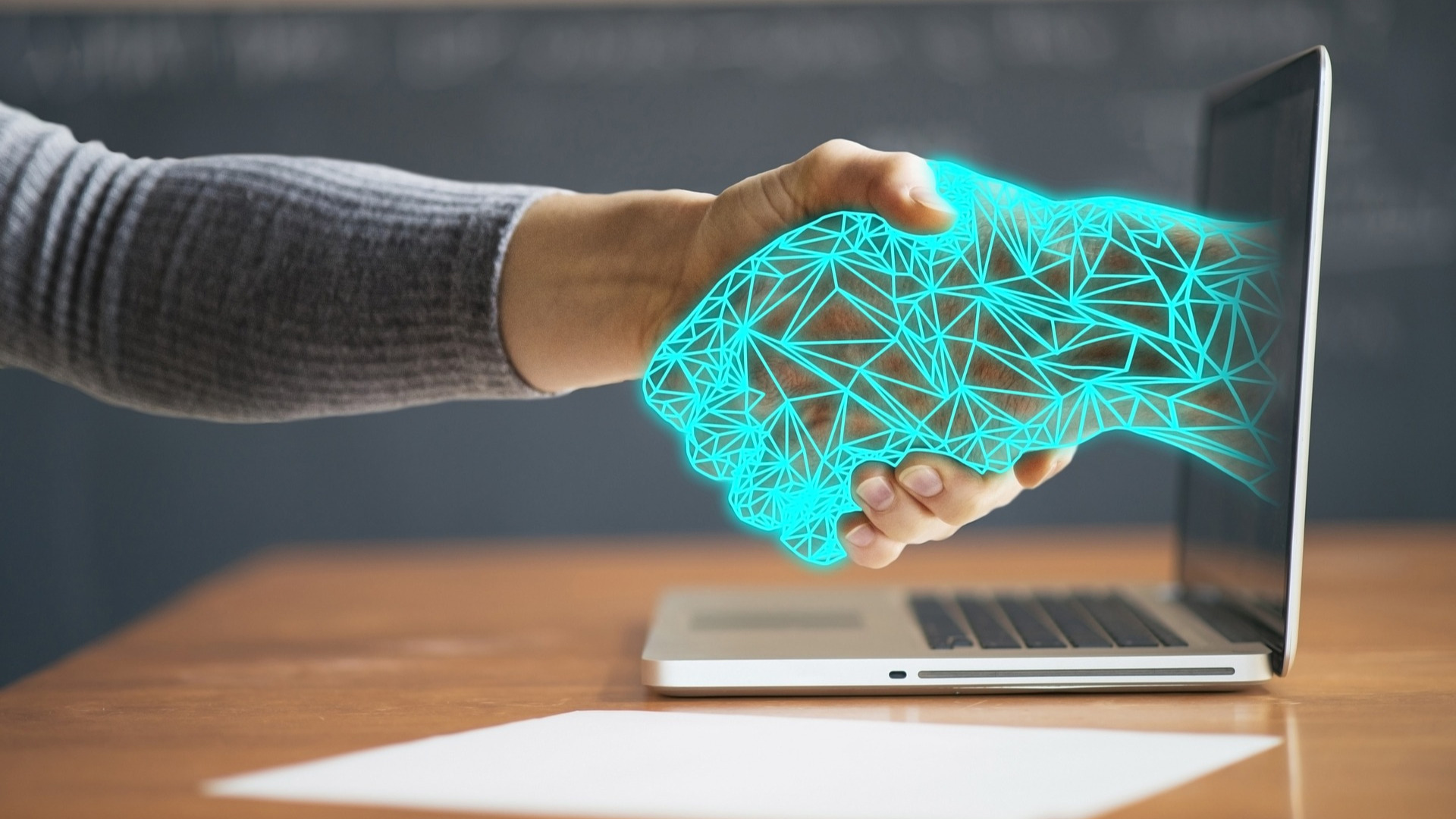
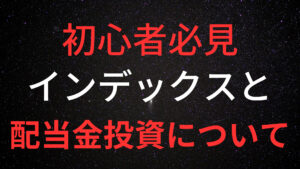
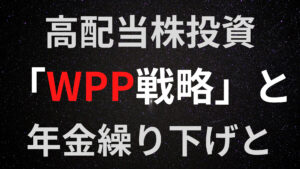
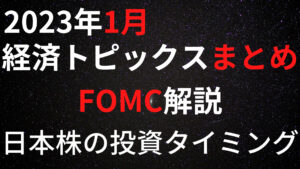
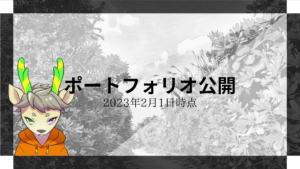

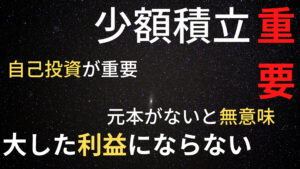
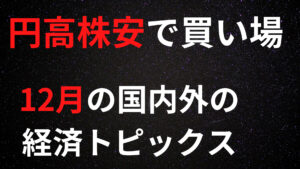
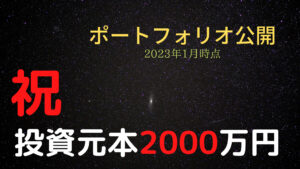
コメント