「仕組み債」による投資のトラブルが増えています。
仕組み債は債券の一種で、仕組み債のパンフレットには「利率1~2%」などの文言が踊っているので、銀行預金よりも高い収益を得たいと考えている人から人気があります。
実際、金利がゼロに近い預貯金では資産が増えないことから、「安全かつ少しでの高利回りの商品を持ちたい」と考え、金融機関などから勧められて買ってしまう人は少なくありません。
しかし、結論からお伝えすると、資産形成をする上での投資商品の選定をするにあたり、仕組み債は除外するべき商品です。
償還時に元本を毀損してしまうなど、高齢者を中心にトラブルの相談が多い投資商品ですが、年齢に関係なく「仕組み債」の特徴について知っておくことは有意義です。

今回は、仕組み債の特徴や投資商品としておすすめできない理由などを紹介していきます。
そもそも「仕組み債」とは?


金融庁の調査によると、地銀での仕組み債の販売額は過去4年間で倍近くに増えています。
「仕組み債」とは債券の一種で、は債券と金融派生商品(デリバティブ)を組み合わせています。一般的な債券は償還期限が定められており、保有期間中はあらかじめ決められた金利が支払われる仕組みです。
基本的には償還時に必ず元本が戻ってくるため、株式よりもリスクが低い投資商品として知られており、多くの投資家から「リスクフリー商品」として活用されています。
しかし、仕組み債は一般的な債券とは異なる特別な「仕組み」を持っており、スワップやオプションなどのデリバティブを利用している点が特徴です。
通常よりも高い金利が得られるメリットがある一方で、特定の株価指数や株価の値動き次第で元本を毀損する可能性があり、実際に大幅に元本が毀損して償還される可能性があるので要注意です。
ざっくりとしたイメージだと、「仕組み債購入後、日経平均株価が購入時よりも30%下がったら投資元本の30%が毀損する」という感じです。
仕組みを十分に理解していない購入者とのトラブル件数が多いことから、メガバンクの三井住友銀行と地方銀行の千葉銀行は仕組み債の販売を全面的に停止しました。
また、みずほフィナンシャルグループと横浜銀行、広島銀行は販売を一部停止する方針を表明しています。
つまり、販売する金融機関としても、今後ますます仕組み債の取り扱いを縮小していくと考えられます。
スワップやオプションの意味
「スワップ」は金利や通貨を交換する取引で
「オプション」は事前に約束した価格で将来的に売買できる権利です。
一般の投資家にとって、スワップやオプションを用いた投資を行う機会はほとんどないので、なじみが無いという人も多いでしょう。
仕組み債は、スワップやオプションなどの複雑なデリバティブを債券に組み合わせ、元本や利息の支払いに一定の条件を設けることで、一般的な債券よりも高い利回りを設定しています。
例えば、スワップを利用することで、金利が低下した際に受取利息が増加しますが、逆に金利が上昇すると受取利息が減少してしまう仕組みになっています。
「ノックアウト」「ノックイン」に注意
仕組み債のパンフレットを見ると、「ノックアウト」「ノックイン」という文言を頻繁に目にします。
ノックアウトとは、参照している経済指標や株価が一定の水準まで上昇することです。ノックアウトが起きると、当初購入した額面金額で債券が召喚されます。
つまり、ノックアウトが起きると、償還時までの利息がそのまま利益となります。
逆に、ノックインとは、参照している経済指標や株価の価格が一定の水準以下になることです。具体的に、ノックイン判定水準は「対象指数の行使価格×70%」といった形で設定されます。
仕組み債保有中に一度でもノックインが起きると、満期償還金が額面より少なくなってしまう仕組みです。
多くの仕組み債では、「満期受取額が株価に連動するのは、対象としている株価指数や株価があらかじめ決められた価格(ノックイン価格)を一度でも下回った場合」としています。
実際に起きているトラブル相談事例では「購入後にノックインし、その後も株価が低迷したことで大きな損失が出てしまった」というものが多いので、ノックインなどの仕組みを理解しないまま購入してしまっていることが分かるでしょう。



もちろん、ノックインなどの仕組みやリスクについて説明しない金融機関にも問題はありますが、投資家個人としても「仕組みが分からないものには手を出さない」ことが重要と言えるでしょう。
仕組み債の鍵は「プットオプション」


仕組み債の中身を見てみると、多くの商品がオプション取引における「プットオプション」が仕込まれています。
先述したように、オプションとは「約束した価格で将来的に売買できる権利」ですが、プットオプションは「売る権利」です。
つまり、「あらかじめ決められた価格で、将来の決められた時点で売ることのできる権利」であり、価格の下落にヘッジする性格を持っています。
プットオプションの仕組み
具体的なケースで見てみましょう。
オプションの買い手は「12月31日までに、商品を1000円で売ることができる権利」を買っていたとします。
期日である12月31日になり、商品が800円に下落している場合は「プットオプションを行使」することで、売り手に対して下落する前の価格で買い取るように請求できるので、オプションの買い手が利益を得ることができます。
しかし、商品が1200円に上昇している場合は、プットオプションを行使すると損をしてしまうため、この場合はオプションの行使を見送ることになります。
このように基本的に「プットオプション」は、商品(株価)の下落に備えるヘッジとして活用できるデリバディブです。
一見すると、リスクヘッジに有効なプットオプションですが、オプションを買うためには売り手に対して「オプション料」を払わなければなりません。
つまり、オプション料は「掛け捨て保険料」と性格が同じで、もしオプションの行使期間中に商品の下落が起きなければ支払った保険料は無駄になります。
プットオプションは売り手のリスクが大きい
「プットオプションを売る」という行為は、つまり「売る権利を売る」ということになります。(ややこしいですが)
もし、商品価格が下落してオプションの買い手が権利を行使して買い取りを要求した場合、当然ですがオプションの売り手は応じなければなりません。
また、オプションは期間内であれば「いつでも権利を行使」できる(つまり、オプションの期日が年末までの場合、それまでの間であればいつでも買い取りを請求できる)ため、いつ要求してくるのかは完全にオプションの買い手次第です。
つまり、オプションの売り手の利益はオプション料に限定されるのに対して、被ってしまう可能性のある損失は計ることができません。
このように、オプション取引は売り手にとってリスクが大きいことを知っておきましょう。
仕組み債にプットオプションを盛り込む問題点


それでは、仕組み債にプットオプションを盛り込むことで、どのような問題が発生するでしょうか?
仕組み債を買うことで、仕組み債の買い手である個人がプットオプションの売り手として「商品の下落に対する保険を引き受ける」ことになります。
先述したように、プットオプションは売り手にとって不利な性格を持っていますが、仕組み債を購入することで「気付かない内にプットオプションの売り手になっている」のです。
保険会社であれば、リスクを引き受ける対価として相応の手数料を受け取ることでビジネスが成立します。しかし、個人投資家は相応の手数料を受け取ることはできません。
これにより、「一般的に安全である債券」というイメージと裏腹に、投資家個人が大きなリスクを背負っている点が仕組み債の大きな問題なのです。
「仕組み債」がおすすめできない理由
冒頭でもお伝えしたとおり、仕組み債は購入する価値の無い投資商品です。
仕組み債がおすすめできない理由について整理してお伝えしていきます。
リターンが低くリスクが大きい
仕組み債がおすすめできない大きな理由は、「リターンが低い割にはリスクが大きいから」です。
投資の世界では「ローリスク・ローリターン」「ハイリスク・ハイリターン」が常ですが、仕組み債は「ハイリスク・ローリターン」なので論外と言えるでしょう。
多くの仕組み債の利率は1~2%程度ですが、ノックインが起こると元本が毀損してしまうことを考えるとリスクとリターンがアンバランスと言わざるを得ません。
仕組み債の買い手が得られる利益は株価指数や株価はいくら上がっても予め決められた金利だけであるのに対して、下落によって生じる損失は計ることができない以上、「買い手にとって不利」です。
また、自分自身で株式連動の投資信託や個別株を買えば、上昇によるリターンが享受できますが、仕組み債の場合は株価上昇によるリターンが享受できない点も大きなマイナスポイントと言えます。
手数料が高い
通常、仕組み債の手数料は5~7%程度ですが、これは投資信託などと比較しても極めて高い水準にあります。
例えば、全世界株式に投資するインデックスファンドやS&P500指数に連動するインデックスファンドでは、信託報酬が0.2%程度のものが多いです。
手数料は投資家にとっては投資のパフォーマンスを損ねる確実なマイナスリターンなので、できるだけ回避するべきコストです。
逆に考えると、金融機関が仕組み債を売り込んでくるのは「自分たちが儲かるから」に他なりません。
そのため、もし金融機関から熱心に仕組み債を売り込まれたとしても、「基本的に拒否」というスタンスでいましょう。
まとめ
仕組み債は「債券の一つ」であることに変わりは無いので、高いリスクは背負いたくない高齢者や投資初心者が目を奪われがちです。
しかし、投資の神様であるウォーレン・バフェットも「分からないものには投資しない」と述べている通り、仕組みが複雑な投資用品や意味が分からない文言が含まれている投資商品には安易に手を出すべきではありません。
仕組み債は「投資に不慣れな人ほど被害を受けやすい」という特徴がありますが、投資初心者や上級者に関係なく、購入を検討する価値が無い投資商品と認識しておきましょう。
今後も自分自身の資産を守るためにも、話題になっている投資商品の本質や仕組みを把握し、自分の価値観に合っているかどうか確認してみてください。

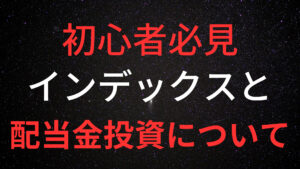
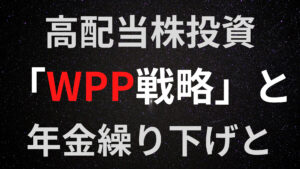
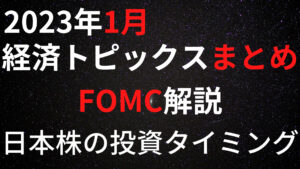
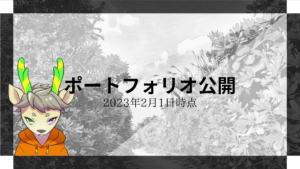

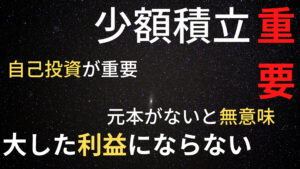
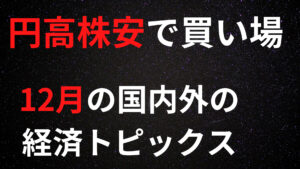

コメント